初老初級ジャグラーの日記です。
ジャグリングを始めたのは2004年。ボールと傘を中心に投げたりまわしたりしてます。2005年1月にクラブを始めましたが、いまだに3クラブカスケードしかできません。花籠鞠、一つ鞠も始めましたが、まだ基本パターンもできません。
技の習得には通常言われている期間の4倍から5倍かかりますが、投げていること自体が好きなのでじわじわ続けています。
カレンダー
| 01 | 2025/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ブログ内検索
カテゴリー
最新TB
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
書名:日本遊戯史―古代から現代までの遊びと社会
著者:増川宏一
出版社: 平凡社 (2012/2/10)
ISBN-10: 4582468144
内容紹介:
記録に現れた古代の遊戯から創造と転換期の中世、多様で華麗な世界の近世を経て、近現代の隆盛と変貌へと至る日本の遊びを文化史として記述した、第一人者による初の全史。
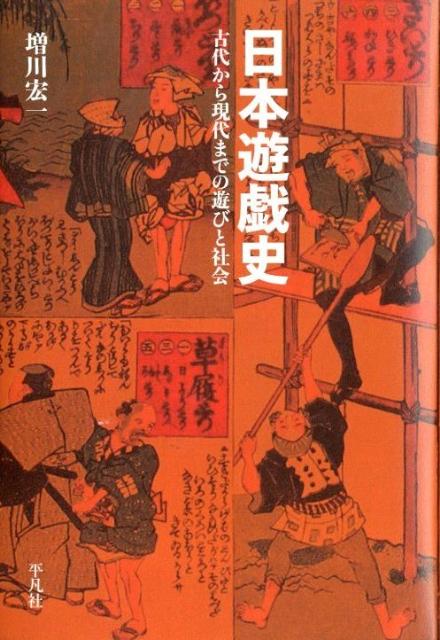
お手玉など遊びの中でのジャグリングに関する言及があるかと思って読んだが、存在しなかった。残念!
しかし遊戯史に関する参考資料のまとめがあったので、役に立ちそう。
まずは酒井欣の『日本遊戯史』を読む!
著者:増川宏一
出版社: 平凡社 (2012/2/10)
ISBN-10: 4582468144
内容紹介:
記録に現れた古代の遊戯から創造と転換期の中世、多様で華麗な世界の近世を経て、近現代の隆盛と変貌へと至る日本の遊びを文化史として記述した、第一人者による初の全史。
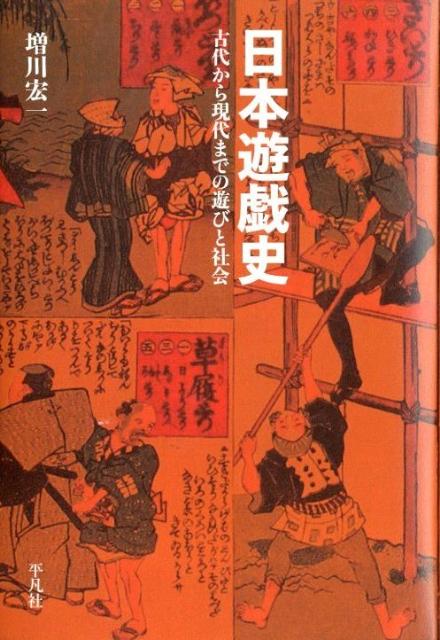
お手玉など遊びの中でのジャグリングに関する言及があるかと思って読んだが、存在しなかった。残念!
しかし遊戯史に関する参考資料のまとめがあったので、役に立ちそう。
まずは酒井欣の『日本遊戯史』を読む!
PR
題名:収蔵資料展覧博物館コレクション 絵巻で見る江戸時代絵巻鑑賞ミニ講座「庶民の世界 ー 江戸風俗絵巻」
日時:2013年7月7日14:00-15:10
料金:200円
会場:横浜市歴史博物館講堂
座席:2列目中央
講師:小林紀子(横浜市歴史博物館近世担当)
客層はほとんどがお年寄り、100人ははいっているでしょうか、興味を持った人が多い
のにびっくり。当初研修室を予定していたが、急遽会場を講堂に代えたのだそうです。
さてプロジェクターと配布資料を使って講義が始まりました。
展示している絵巻物三種の内容解説と実物をガラス越しでなく見る体験です。
・展示目的
今回の展示は絵巻物だけの展示であり、江戸時代の様子を描いているもの。この博物館で
集めてきたもの、という条件で選択した。内容に関するテーマを決めると通常の企画展と
変わらなくなるのであえて内容で絞りこんでいない。
博物館は横浜に関係するものを集めて残していくというのが大きな役割としてあり、
横浜と江戸時代に関連するものを集めている。
絵巻物は長いのですべてを同時に見せることはなかなかできない。展示室の中でも季節に
かかわるものとか、見せたい箇所をみせている。
今回の企画は閉じているところも見てもらおうという意図がある。
・絵巻1 風俗絵巻
作者不詳・江戸時代・24*838.5cm
前半に魚の競りと魚を運ぶ様子、後半は宴会とマキ売り、冒頭に漢詩。
競りはマグロ、魚の書き方、わりとちゃんとしている。
車の上に巨大たこを載せてひっぱっている。腰に黄色い物、煙管と煙草いれ。
ひとりひとりの表情が違っておもしろい。巨大エビも運ぶ。
魚が巨大だったのは豊漁を示しているのかもしれない。
その後宴会の様子。目隠し鬼をして遊んでいるシーン。
薪売りは、おはらめ(京都の大原からくるひとたち)がモデルではないか。
展示室では冒頭からタコのシーンを展示している。
・絵巻2 四季農耕絵巻
狩野玉燕筆、青亀斎写
写した日が文化11年(1814)。狩野玉燕は幕府御用絵師で(1683-1743)
青亀斎は紺屋で戸塚に住んでおり、青木友八が本名。60過ぎてから旅に出て
「戸塚宿紺屋友八西国旅日記」を書き記している。
苗代、種まき、馬鍬でしろかき、焼き米つき、煎り米、田植え、が見える
遊んでいるように見えるひとたちは田楽と言われるものと考えられており、
よくあるモチーフ。座頭が描かれているが、普通にいたと思われる。
最後の収穫シーンでは門付に猿回しがきている。
この図では稲刈りからよりわけて俵に積めているが脱穀が書いてない。
農耕図は中国からはいってきている。
日本では戦国時代で中国のものを狩野派がうつしてきて、レパートリーとした。
中国の図を絵画的に写してきているので細かく全部書くのではなく、余白をとり
いれてシーンをすっきりした。中国の農耕図は納めている側の人たちにみせるもの、
農業はたいへんで苦労しながら税金を納めている、そういうことで描かれた。
どこかがモデルになっているとかそういうことではない。この農耕図を書き写す
段階で、服装などは江戸時代のものに置き換えられている。
・風俗画巻
東陽・江戸時代・20.6*662cm
江戸時代の生活の様子を描いた作品。東陽という署名があるが、詳細は不明。
もしかしたら幕末??
まりつき、凧揚げなどが描かれている。
凧揚げは男性が凧糸を持って上を向いていて、その隣に子供が上を向いている。
絵の中には凧が描かれていない。糸と目線だけで凧揚げを示している
トンビに魚を攫われた中間の姿が描かれているが、「鳶奴」という歌舞伎から
きているのではないか。
そして最後に檀上に絵巻物を展示して、皆で鑑賞。
ここで講座は終了、その後講師の方を取り囲んで(^^;) 質疑応答。
-私のQ
田楽?という場面があるが、模写だとすると実際にこのようなことが行われていた
わけではない?田楽でどのような曲芸が行われていたのか興味があるのだが、
他の絵に心当たりはありませんか?
-A
様式を書き写しているので、そこで行われていたということではないと思われる。
農耕図に関しては町田市博物館の図録にあったと思うので、図書室で調べてみると良い。
----ここまで講座メモ---
そういうわけで、歴史博物館の図書室にいって田楽の資料を探索してみました。
司書の方の助力もありつぎのような資料を発見。
1.「農耕図と農耕具展」町田市立博物館図録 第85集(1993年)
2.「王子田楽総合調査報告書」東京都北区教育委員会 [編](1988年)
1番では「堀家本四季農耕絵巻」で田んぼの中で笛太鼓で踊っている姿。
2番では「法然上人絵伝」で太鼓を打ち鳴らし、そして上向いて放り投げて
いる姿。こちらは農耕絵巻の田楽部分とかなり似たテイスト。同じ絵をまねたのかも。
農耕図を狩野派で書き写されていたという話は今回かなりありがたいお話でしたね。
それにしても田楽曲芸は田んぼではやっていなかったのか??
謎は深まるばかりです。
今日は昼間はジャグリング協会総会、夕方から両国パフォーマンス学会。
ジャグリング協会総会では昨年度の決算の承認と今年度の予算案の承認が行われた。
総会の後は日頃なかなか集まれない理事全員で、face to face での意見交換。
課題はいっぱいあるのだけれどがんばっていきましょう。
JJF2013ももうすぐなのよね。
そしてその足で両国へ。。

題名:第一回両国パフォーマンス学会
日時:2013年6月29日15:00-20:00(その後懇親会)(18時少し前から参加)
場所:両国門天ホール
料金:聴講のみ2,000円/発表者1,000円(懇親会費用別途)
URL:http://www.high-beam.info/shinnosuke/meeting
趣旨:
昨今、ジャグリング、サーカス、あるいは大道芸に対して、実践のみならず、様々な見地から
論考を進める方が増えて来ているように感じます。「両国パフォーマンス学会」では、その道
の専門家から専門家を志す方までが、互いに日頃の研究成果を発表し、交流する場を設けるこ
とを趣旨とします。
ジャグリング協会総会と重なったので途中参加。冒頭から聞きたかったOrz
目黒さんのインタビューから聞くことになりました。
☆目黒陽介(プロジャグラー)【インタビュー】「ながめくらしつについて」(聞き手 しんのすけ)
-しんのすけ(以降し)
パフォーマンスの構成はどのように創造?
-目黒(以降め)
わりと絵が最初にでてくることがおおい。
最初から順番があるわけじゃない。
―し
観客のジャグラー比率は?
ジャグリングは世間にどれくらいひろまっているのか
ーめ
まったく広まっていない
3月公演はジャグラー比率多かった。
ジャグラーがみて、なにかをやるきっかけになればいいなあ。
いろいろ理由をつけてやらないのは無し。
やろうかどうしようかなということならやればよい
☆大平道介「映像解析による3ボールカスケード習得過程の分析」
全員がまったくジャグリングできないという状態で被験者になってもらい習得課程を記録した。
基本的には自由に練習していただいて、その日テストとヒアリングを行った。
テスト時に録画して映像解析とヒアリング。
主観と客観をまぜた解析を行ったというのが先行研究との違い。
上達とともに失敗原因が変化していくのがわかった。
練習すれば上達するということがわかった。しかし練習しなくても上達することがある。
☆しんのすけ「ジャグリング講師の現状と可能性」
カルチャースクールにおいて週3回6教室合計38人にジャグリングを教えている。
これで月6万円の収入。その他個人レッスン。
タレントさんへの個人指導がはいるとおいしいが1年に一度あるかないかの頻度。
たまに企業研修がはいる。
生徒さんが支払っている受講料の4割弱がこちらの収入だった。
他でもそう変わらないようだが、最近は割合がだんだん下がっているようだ。
どうやってぽつぽつの収入をコンスタントにするか?
ひとつのアプローチとしてはジャグリングが役に立つということから攻める。
ダンディGOさんは、ジャグザサイズとして一般の人にできる形で切り込んでいる
記憶力の大会で直前にジャグリングをする姿がみられるそうだ。ジャグリングに
より能力向上が見られるとのこと。
教室はアマチュア向けが多い、プロ向けとするにはターゲットを明確にして効能
をつけて教室を立ち上げる必要があると思われる。
質疑応答
ーQ
個人営業はどのように?
ーA
ホームページにかいている。ツイッターなどで随時発信している。
競争相手がいないので問い合わせがくればまず成約になる。
ーQ
ダンサーとかミュージシャンは教えることで食えている人が多い。
そもそも人口も多い。でも生徒さんは必ずしも舞台を見にこない。
教室を続けていってもアーティストとして活躍できる場があるわけではない。
講師をしていくことがどれくらい有効であるのか?
ーA
アーティストというポジションは狙っていない。
舞台でも講師でも選択肢があるのがいいのだと思う。
見ることとやることの断絶はやはりある。
ーQ
講師の対極にあるのがサークル。
サークルに行きさえすればただで教えてもらえるのに
なぜ人はお金を払って教室に通うのか?
ーA
知らない人のところに飛び込めない人がいる。
また教わりたいと思う人がいる。
ーコメント
10年以上自分のスタジオで教室をやっている。生徒は一番多い時で10人程度。
自宅で練習してこなくて、教室でコミュニケーションとりたい人が多かった。
メンバー固定になり、遊びにくる感覚になっていたようだ。
子供はもっとやりたい、もっとうまくなりたいという者が多い。
教室によって雰囲気が違う。
発表会をたてるとみんなやめない。
☆津村大樹「変容する大道芸とプラットフォームの重要性」
大道芸フェスティバル等で大道芸観賞は若者の趣味となった。
大道芸ファンがふえているにもかかわらず、必要とされているプラット
ホームが不足しているのではないか。検索しても場所がわからないので行けない等。
そこでGoogleアースを使ってパフォーマンスポイントをアーカイブしていこうと企画した。
大道芸のアーカイブは行われておらず後世に情報を残したい。
-Q
大道芸はどこまで?
-A
ストリートミュージシャンは入れない
とりあえずは大道芸フェスティバルを想定している
路上に限っている。
-Q
クラウドで皆で入力する形をとる?
-A
とりあえずはひとりで、まずは2014までを残そう
☆くろせひろやす「日本の中世におけるジャグリングについて」
私の発表予稿はこちら
-Q
歴史の専門家は何をやっていたかまで踏み込めない。その道のスペシャリストが見れば別のことがわかるかもしれないと私も考えたことがある。「中世」とタイトルにあるがこの発表の範囲は「古代から中世」ではないか
-A
そのとおり。当初は中世だけを解説するつもりで「中世」というタイトルにしたが、やはり通して説明する方がわかりやすくなると思い、古代から中世までの発表にしてしまった。
-Q
いま残っている散楽的要素は各地に残っている。伊勢太神楽や千葉における蜘蛛舞、高足、刀を使った神楽等。
ジャグリングを日本文化であるとすればいま残っているものに興味を持ってほしい
-A
私も江戸太神楽を学んでいる。綱渡りもおもしろいのだけれど、話が広くなりすぎるのでとりあえず別に考えている。
-Q
いろんな人がそれらの範疇を出入りしているので、視野を広くとらえておく方が良いのではないか
-A
アンテナは広くしておきたいと思っている。
-Q
江戸時代の手品について研究している。先週中世の手品について発表したばかり。
資料はプロのひとたちが職業としてなしていたもの。中世に趣味として演じていたものはないか。
私が見つけたのは年中行事絵巻の中で子供が遊んでいるもの。年表は年代と技の内容に注目して
まとめているが、どういう人や場所に注目するのも大切だと思われるがどう考えているか
-A
文書として残っているもので把握できているのは天皇や貴族の前で上演されたもののみ。
私はジャグラーなので何をやっていたかが一番気になっているが、演者や演じられた状況にも興味を持っている
遊びとして何が行われていたか?ということも気になっているが、遊びについては江戸時代まで下れば
いくつか文献があるが、それ以前ではまだみつけられていない。もし見つけたら私にも教えてほしい
☆上島敏昭(大道芸人 大道芸研究者)「大道芸からパフォーマンスへ・・・その連続性と断絶と」
70年代で小沢昭一が放浪芸のレコードを出した。
80年代になって坂野比呂志が大道芸をタイトルに掲げた内容の上演をするようになった。
昔はこういうことをやっていたとして大道芸をとりあげた。
がまのたたき売り、口上芸、舞台芸であるにもかからわず大道芸となった
1990年代、大道芸大会ができてきた。最初に大須、つぎに横浜で大道芸大会が発生。
とにかく街頭でやっちゃえ、それが大道芸。
絵解き、人間ポンプ、伝統的な大道芸がメインだったのが、ジャグリング、パントマイム
に変わっていった。パフォーマンスと呼ばれるのもそれ以降である
国会図書館キーワード検索で大道芸、放浪芸、パフォーマンスを検索した。
残念ながらパフォーマンスは性能などで使われていて意図した検索は困難。
1980年代現代用語の基礎知識、現代美術用語の解説でパフォーマンスがでる。
1985年がピーク パフォーマンスが流行語大賞、パフォーマンスが一般化。
朝日年鑑1984年版 芸能の分野、新劇、商業、伝統弦劇、寄席、エンターテインメント、舞踏。
85年、パフォーマンス、ダンスが追加されている、エンターテインメント、舞踊がなくなる。
パフォーマンスといえば 古事記の物乞いのしかた
パフォーマンスと名乗った表現がふえてきたころ、パフォーマンスと言えば
ローリーアンダーソン、ナムジュンパイク、如月小春だった。
60年代はハプニングと呼ばれていた。赤瀬川源平がその典型。
白衣をきて防塵マスクをして、メガネをしてほうきをもって集団で石灰を散布する
道具をもって街中、銀座に繰り出しておそうじパフォーマンス。伝染病でないかといわれた。
お札の模写を作品として発表、偽札事件になった。
そして裁判の記録と証拠品としてアートとして展示した。
秋山祐徳太子は東京都知事に立候補で有名。
80年代のパフォーマンスは、一発芸、その時代の雰囲気を味わないとわからない。
1980年 竹の子族 ローラー族、1981年 おれたちひょうきん族、
1984 CDプレイヤー、スリラー 映像がついた音楽、ロス疑惑。
原宿でみんなが踊っていた、ピーターフランクルも一世風靡セピアもいた。
高足、ジャグリング、パントマイム、街頭演劇いっぱいあった。
これは四条河原?原宿は渋谷と新宿の警察のあいだで権力の空白地帯。
反閇も見た!
それまでの大道芸とよばれるものと、竹の子族以降はパフォーマンスは違うもの。
1986年横浜でやったのは原宿のお祭り気分を継いでいる。
失われた20年が現在の大道芸の歴史。
バブルの芸能はかなりおおきなものになる。
85年以降のパフォーマンスははバブルの申し子だったのだろう

☆☆私の感想
皆がジャグリングやパフォーマンスを愛していて、皆に語りたい!という思いがとてもよく
あらわれていた場だった。それゆえとてもクロスオーバーなジャンルではあるが
それらすべての「愛」が伝わり、楽しい雰囲気がずっと続いていたのだと思う。
この機会を提供してくれたしんのすけさんに感謝。
この場をつくりあげた発表者、参加者の皆さんにも感謝。
かなりいろいろギリギリだったのですが、発表してよかった!
懇親会も大勢のかたと意見交換・名刺交換ができてたいへん楽しい時間をすごせた。
楽しすぎて、料理ほとんど食いそびれた(涙) でもカレーだけはしっかり食わせてもらいました
美味しかった。
そして最後の最後に残ったひとたちで二次会へ。
終電で帰るはずが2本目に乗った地下鉄が微妙に遅れて、途中からタクシー Orz
ほんとに盛り沢山な1日でしたよ
写真は二次会、みなさんお疲れ様でした。

ジャグリング協会総会では昨年度の決算の承認と今年度の予算案の承認が行われた。
総会の後は日頃なかなか集まれない理事全員で、face to face での意見交換。
課題はいっぱいあるのだけれどがんばっていきましょう。
JJF2013ももうすぐなのよね。
そしてその足で両国へ。。
題名:第一回両国パフォーマンス学会
日時:2013年6月29日15:00-20:00(その後懇親会)(18時少し前から参加)
場所:両国門天ホール
料金:聴講のみ2,000円/発表者1,000円(懇親会費用別途)
URL:http://www.high-beam.info/shinnosuke/meeting
趣旨:
昨今、ジャグリング、サーカス、あるいは大道芸に対して、実践のみならず、様々な見地から
論考を進める方が増えて来ているように感じます。「両国パフォーマンス学会」では、その道
の専門家から専門家を志す方までが、互いに日頃の研究成果を発表し、交流する場を設けるこ
とを趣旨とします。
ジャグリング協会総会と重なったので途中参加。冒頭から聞きたかったOrz
目黒さんのインタビューから聞くことになりました。
☆目黒陽介(プロジャグラー)【インタビュー】「ながめくらしつについて」(聞き手 しんのすけ)
-しんのすけ(以降し)
パフォーマンスの構成はどのように創造?
-目黒(以降め)
わりと絵が最初にでてくることがおおい。
最初から順番があるわけじゃない。
―し
観客のジャグラー比率は?
ジャグリングは世間にどれくらいひろまっているのか
ーめ
まったく広まっていない
3月公演はジャグラー比率多かった。
ジャグラーがみて、なにかをやるきっかけになればいいなあ。
いろいろ理由をつけてやらないのは無し。
やろうかどうしようかなということならやればよい
☆大平道介「映像解析による3ボールカスケード習得過程の分析」
全員がまったくジャグリングできないという状態で被験者になってもらい習得課程を記録した。
基本的には自由に練習していただいて、その日テストとヒアリングを行った。
テスト時に録画して映像解析とヒアリング。
主観と客観をまぜた解析を行ったというのが先行研究との違い。
上達とともに失敗原因が変化していくのがわかった。
練習すれば上達するということがわかった。しかし練習しなくても上達することがある。
☆しんのすけ「ジャグリング講師の現状と可能性」
カルチャースクールにおいて週3回6教室合計38人にジャグリングを教えている。
これで月6万円の収入。その他個人レッスン。
タレントさんへの個人指導がはいるとおいしいが1年に一度あるかないかの頻度。
たまに企業研修がはいる。
生徒さんが支払っている受講料の4割弱がこちらの収入だった。
他でもそう変わらないようだが、最近は割合がだんだん下がっているようだ。
どうやってぽつぽつの収入をコンスタントにするか?
ひとつのアプローチとしてはジャグリングが役に立つということから攻める。
ダンディGOさんは、ジャグザサイズとして一般の人にできる形で切り込んでいる
記憶力の大会で直前にジャグリングをする姿がみられるそうだ。ジャグリングに
より能力向上が見られるとのこと。
教室はアマチュア向けが多い、プロ向けとするにはターゲットを明確にして効能
をつけて教室を立ち上げる必要があると思われる。
質疑応答
ーQ
個人営業はどのように?
ーA
ホームページにかいている。ツイッターなどで随時発信している。
競争相手がいないので問い合わせがくればまず成約になる。
ーQ
ダンサーとかミュージシャンは教えることで食えている人が多い。
そもそも人口も多い。でも生徒さんは必ずしも舞台を見にこない。
教室を続けていってもアーティストとして活躍できる場があるわけではない。
講師をしていくことがどれくらい有効であるのか?
ーA
アーティストというポジションは狙っていない。
舞台でも講師でも選択肢があるのがいいのだと思う。
見ることとやることの断絶はやはりある。
ーQ
講師の対極にあるのがサークル。
サークルに行きさえすればただで教えてもらえるのに
なぜ人はお金を払って教室に通うのか?
ーA
知らない人のところに飛び込めない人がいる。
また教わりたいと思う人がいる。
ーコメント
10年以上自分のスタジオで教室をやっている。生徒は一番多い時で10人程度。
自宅で練習してこなくて、教室でコミュニケーションとりたい人が多かった。
メンバー固定になり、遊びにくる感覚になっていたようだ。
子供はもっとやりたい、もっとうまくなりたいという者が多い。
教室によって雰囲気が違う。
発表会をたてるとみんなやめない。
☆津村大樹「変容する大道芸とプラットフォームの重要性」
大道芸フェスティバル等で大道芸観賞は若者の趣味となった。
大道芸ファンがふえているにもかかわらず、必要とされているプラット
ホームが不足しているのではないか。検索しても場所がわからないので行けない等。
そこでGoogleアースを使ってパフォーマンスポイントをアーカイブしていこうと企画した。
大道芸のアーカイブは行われておらず後世に情報を残したい。
-Q
大道芸はどこまで?
-A
ストリートミュージシャンは入れない
とりあえずは大道芸フェスティバルを想定している
路上に限っている。
-Q
クラウドで皆で入力する形をとる?
-A
とりあえずはひとりで、まずは2014までを残そう
☆くろせひろやす「日本の中世におけるジャグリングについて」
私の発表予稿はこちら
-Q
歴史の専門家は何をやっていたかまで踏み込めない。その道のスペシャリストが見れば別のことがわかるかもしれないと私も考えたことがある。「中世」とタイトルにあるがこの発表の範囲は「古代から中世」ではないか
-A
そのとおり。当初は中世だけを解説するつもりで「中世」というタイトルにしたが、やはり通して説明する方がわかりやすくなると思い、古代から中世までの発表にしてしまった。
-Q
いま残っている散楽的要素は各地に残っている。伊勢太神楽や千葉における蜘蛛舞、高足、刀を使った神楽等。
ジャグリングを日本文化であるとすればいま残っているものに興味を持ってほしい
-A
私も江戸太神楽を学んでいる。綱渡りもおもしろいのだけれど、話が広くなりすぎるのでとりあえず別に考えている。
-Q
いろんな人がそれらの範疇を出入りしているので、視野を広くとらえておく方が良いのではないか
-A
アンテナは広くしておきたいと思っている。
-Q
江戸時代の手品について研究している。先週中世の手品について発表したばかり。
資料はプロのひとたちが職業としてなしていたもの。中世に趣味として演じていたものはないか。
私が見つけたのは年中行事絵巻の中で子供が遊んでいるもの。年表は年代と技の内容に注目して
まとめているが、どういう人や場所に注目するのも大切だと思われるがどう考えているか
-A
文書として残っているもので把握できているのは天皇や貴族の前で上演されたもののみ。
私はジャグラーなので何をやっていたかが一番気になっているが、演者や演じられた状況にも興味を持っている
遊びとして何が行われていたか?ということも気になっているが、遊びについては江戸時代まで下れば
いくつか文献があるが、それ以前ではまだみつけられていない。もし見つけたら私にも教えてほしい
☆上島敏昭(大道芸人 大道芸研究者)「大道芸からパフォーマンスへ・・・その連続性と断絶と」
70年代で小沢昭一が放浪芸のレコードを出した。
80年代になって坂野比呂志が大道芸をタイトルに掲げた内容の上演をするようになった。
昔はこういうことをやっていたとして大道芸をとりあげた。
がまのたたき売り、口上芸、舞台芸であるにもかからわず大道芸となった
1990年代、大道芸大会ができてきた。最初に大須、つぎに横浜で大道芸大会が発生。
とにかく街頭でやっちゃえ、それが大道芸。
絵解き、人間ポンプ、伝統的な大道芸がメインだったのが、ジャグリング、パントマイム
に変わっていった。パフォーマンスと呼ばれるのもそれ以降である
国会図書館キーワード検索で大道芸、放浪芸、パフォーマンスを検索した。
残念ながらパフォーマンスは性能などで使われていて意図した検索は困難。
1980年代現代用語の基礎知識、現代美術用語の解説でパフォーマンスがでる。
1985年がピーク パフォーマンスが流行語大賞、パフォーマンスが一般化。
朝日年鑑1984年版 芸能の分野、新劇、商業、伝統弦劇、寄席、エンターテインメント、舞踏。
85年、パフォーマンス、ダンスが追加されている、エンターテインメント、舞踊がなくなる。
パフォーマンスといえば 古事記の物乞いのしかた
パフォーマンスと名乗った表現がふえてきたころ、パフォーマンスと言えば
ローリーアンダーソン、ナムジュンパイク、如月小春だった。
60年代はハプニングと呼ばれていた。赤瀬川源平がその典型。
白衣をきて防塵マスクをして、メガネをしてほうきをもって集団で石灰を散布する
道具をもって街中、銀座に繰り出しておそうじパフォーマンス。伝染病でないかといわれた。
お札の模写を作品として発表、偽札事件になった。
そして裁判の記録と証拠品としてアートとして展示した。
秋山祐徳太子は東京都知事に立候補で有名。
80年代のパフォーマンスは、一発芸、その時代の雰囲気を味わないとわからない。
1980年 竹の子族 ローラー族、1981年 おれたちひょうきん族、
1984 CDプレイヤー、スリラー 映像がついた音楽、ロス疑惑。
原宿でみんなが踊っていた、ピーターフランクルも一世風靡セピアもいた。
高足、ジャグリング、パントマイム、街頭演劇いっぱいあった。
これは四条河原?原宿は渋谷と新宿の警察のあいだで権力の空白地帯。
反閇も見た!
それまでの大道芸とよばれるものと、竹の子族以降はパフォーマンスは違うもの。
1986年横浜でやったのは原宿のお祭り気分を継いでいる。
失われた20年が現在の大道芸の歴史。
バブルの芸能はかなりおおきなものになる。
85年以降のパフォーマンスははバブルの申し子だったのだろう
☆☆私の感想
皆がジャグリングやパフォーマンスを愛していて、皆に語りたい!という思いがとてもよく
あらわれていた場だった。それゆえとてもクロスオーバーなジャンルではあるが
それらすべての「愛」が伝わり、楽しい雰囲気がずっと続いていたのだと思う。
この機会を提供してくれたしんのすけさんに感謝。
この場をつくりあげた発表者、参加者の皆さんにも感謝。
かなりいろいろギリギリだったのですが、発表してよかった!
懇親会も大勢のかたと意見交換・名刺交換ができてたいへん楽しい時間をすごせた。
楽しすぎて、料理ほとんど食いそびれた(涙) でもカレーだけはしっかり食わせてもらいました
美味しかった。
そして最後の最後に残ったひとたちで二次会へ。
終電で帰るはずが2本目に乗った地下鉄が微妙に遅れて、途中からタクシー Orz
ほんとに盛り沢山な1日でしたよ
写真は二次会、みなさんお疲れ様でした。
今日はさわやかな晴れ、というわけで Bryant Park へGO!
Bryant Park Juggling にお邪魔した。
Bryant Park は42丁目の5ave と6 ave の間にある。NYPLの裏側。
平日の昼休みに集うという感じらしい。
ボールやクラブをたくさん持ってきていて、公園に集まってくる皆さんに貸し出して教えていた。
年配の方にも興味を持ってもらえているのがすごい。
ボール、クラブ、コンタクト、以外にはディアをやっていた方がひとりで、道具の種類はあまりない感じ。まあ日本が多様すぎるのでしょう。私は一応ロープも持っていったけれど狭くて場所がなかったので断念。
初夏のさわやかな陽気の中でみんなとじゃぐるのって気持ちいいですよね。
ちなみにブライアントパークの全景はこんなもの、真ん中が芝生でごろごろと。。
